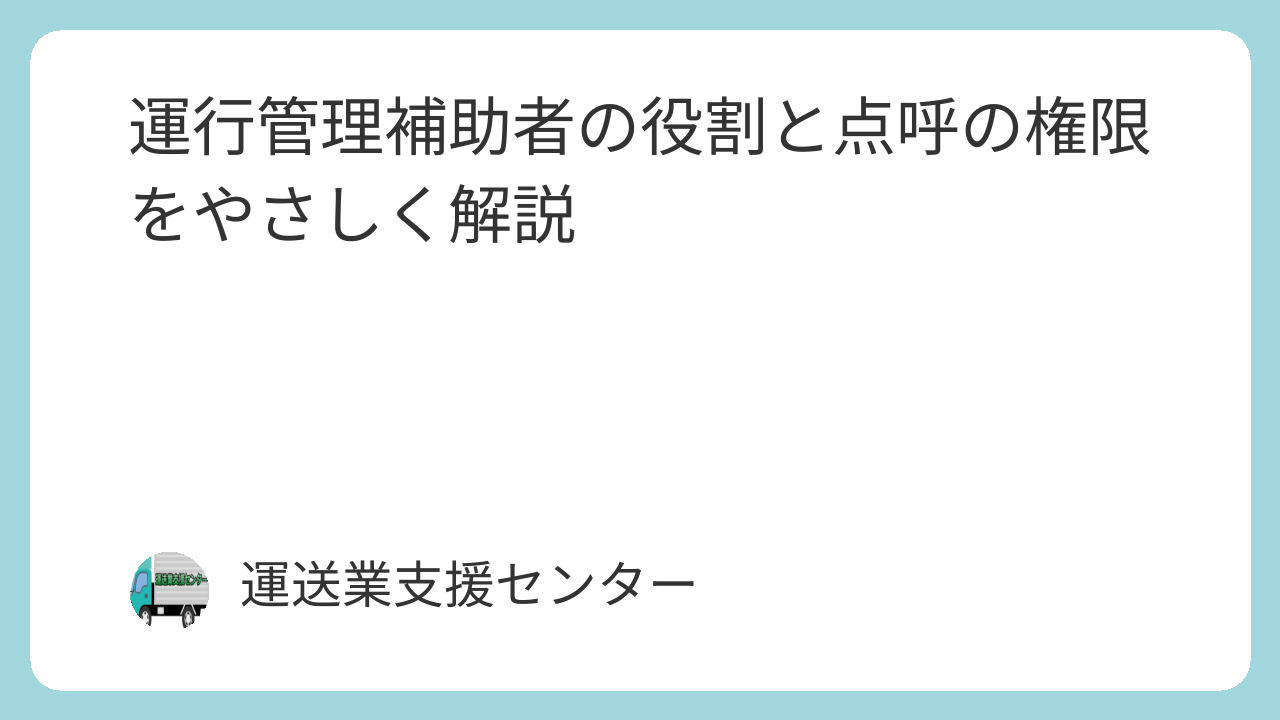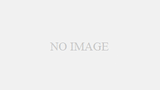運行管理補助者制度の仕組みを丁寧に解説しています。実務に関わる方はもちろん、初めて知る方にもイメージしやすくなるよう心がけました。
はじめに:補助者ってどんな立場?
運行管理補助者とは、トラックや貨物車の運行を安全に行うために必要な「運行管理」の業務を、専門の「運行管理者」のサポート役として手伝う人のことです。
補助者という呼び方から分かるように、あくまで“補助”という立場です。運行管理者の代わりにすべての業務をやるわけではなく、任された範囲内で手助けをする形になります。
点呼ってなに?補助者ができること・できないこと
点呼とは、ドライバーさんが出発前や帰社後に、アルコール検査や体調チェックを行い、安全に運転できるかどうかを確認する大事な業務です。事故を未然に防ぐためにも、とても重要な仕事です。
補助者は、この点呼の一部については「単独で」実施することが認められています。つまり、運行管理者がいなくても、補助者だけで点呼ができる場面もあります。
ただし注意すべきなのは、問題が見つかったときです。たとえば…
| 問題の例 | 補助者の対応 |
|---|---|
| アルコール反応が出た | 管理者に報告して判断を仰ぐ |
| 疲労・病気で安全運転ができなさそう | 補助者だけでは判断せず、必ず報告 |
| 無免許や資格外で運転している | 補助者は即時報告 |
補助者は「問題がないことを確認する」まではできますが、「問題があるかも?」という状況では、自分だけで判断してはいけません。常に運行管理者との連絡が取れるよう、社内では電話やIT機器での連絡手段を整えておく必要があります。
どれくらい点呼できるの?
補助者ができる点呼の割合は、全体の「3分の2まで」とされています。
この“割合”ですが、「日数」ではなく「回数」で数えるのが正しいルールです。
具体例でみてみましょう:
たとえば、10人のドライバーがいて、1人につき「乗務前」と「乗務後」の2回点呼が必要だとすると、1日の点呼は合計で20回となります。
そのうち、補助者が対応できるのは最大13回まで。つまり…
- 朝の点呼は管理者が行い、
- 帰りの点呼は補助者が全員分実施する
という形でもルール上は問題ありません。こうした柔軟な使い方をすることで、運行管理者の負担をうまく減らすことができるのです。
運行管理補助者になるには?
補助者になるためには、一定の資格や経験が必要です。
以下のいずれかを満たしていることが条件です:
- 国の指定する「運行管理者基礎講習」を修了している
- 「運行管理者資格者証」を持っている
講習は、NASVA(自動車事故対策機構)や、国土交通省が認定している民間機関で受けることができます。
参考リンク:
運行管理補助者を選んだらどうするの?
補助者を選任した場合、一般貨物事業では「運輸支局への届出」は不要です。
※貸切バス事業の場合は、軽井沢スキーバス事故をきっかけとして届出が義務付けられました。
ただし、社内でしっかりと周知する必要があります。
社内で行うべきこと:
- 補助者の氏名を、事務所の見やすい場所に掲示する
- 社内規程に「補助者の選任基準・役割・対応ルール」などを明記する
▼【運行管理規程に記載しておくべき内容(例)】
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 補助者の名前 | 誰が担当しているか社内周知を図る |
| 担当範囲 | 点呼の回数・業務内容などを明確に |
| 管理者との関係 | 指示・監督・報告義務の記載 |
| 業務の責任 | 補助者が行った業務の責任は管理者が負う |
他の営業所や事業との兼任は可能
補助者は「旅客事業との兼任」や「複数の営業所での兼任」も認められています。
ただし、その場合は運行管理規程に「管理体制」や「業務分担」などについて明記しておき、無理なく運行管理業務が回るような体制を整える必要があります。
運行管理補助者は講習を受ける義務がある?
2年に1回の「運行管理者一般講習」は補助者に義務づけられていません。
ただし、運行管理者が受けた講習内容を補助者へしっかりと伝え、社内で情報共有することが望ましいとされています。
補助者から運行管理者になるには?
補助者として長く勤めると、運行管理者を目指したくなるかもしれません。
その場合は、5年間の実務経験に加えて、「年1回の一般講習を4年間続けて受講」することが必要です。これを満たせば、資格試験の受験条件をクリアできます。