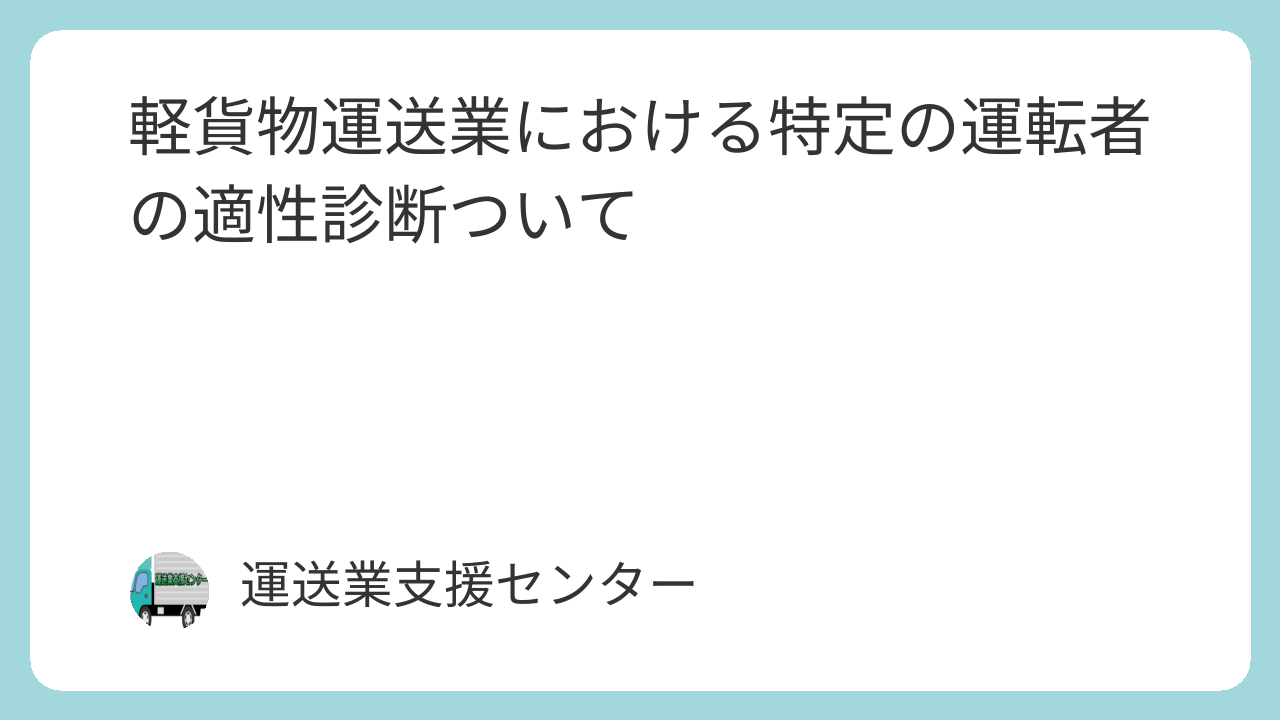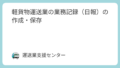適性診断は運転者の運転のクセや傾向を確認するものです。
自動車の運転に関する長所、短所といった「運転のクセ」を様々な測定により見出し、それぞれのクセに応じたアドバイスをうけることで、交通事故防止に活用できます。
指摘が多い場合であっても運転業務を行っていけないというものではありません。
適性診断の結果の確認をすることで、運転者自身の傾向や運転時に注意すべきことなどを正しく理解し、事故防止につなげてください。
適性診断の種類と内容
適性診断には4種類があります。適性診断の種類によって、対象となる運転者や実施内容が異なります。
| 診断の種類 | 対象運転者 | 診断の内容 | 診断時間 |
|---|---|---|---|
| 初任診断 | 初任運転者 | プロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための助言・指導 | 約2時間20分 |
| 適齢診断 | 高齢運転者 | 加齢による影響の認識と事故の未然防止のための助言・指導 | 約2時間20分 |
| 特定診断Ⅰ | 事故惹起運転者Ⅰ | 交通事故の再発防止のための助言・指導 | 約2時間40分 |
| 特定診断Ⅱ | 事故惹起運転者Ⅱ | 運転特性・背景要因の分析と交通事故の再発防止のための助言・指導 | 約5時間 |
| 診断名 | 対象 |
|---|---|
| 初任運転者 | 初めて乗務する運転者 |
| 高齢運転者 | 65 歳以上の者 |
| 事故惹起運転者Ⅰ | 死亡又は重傷事故+過去 1 年間に事故を起こしたことがない者 軽傷事故+過去3 年間に事故を起こしたことがある者 |
| 事故惹起運転者Ⅱ | 死亡又は重傷事故+過去 1 年間に事故を起こしたことがある者 |
受診するタイミング
- 初任運転者:初めて乗務する前(やむを得ない場合は乗務後1か月以内)
- 高齢運転者:65歳に達した日から1年以内
- 事故惹起者:再乗務前(やむを得ない場合は乗務後1か月以内)
記録と保存義務
- 指導・診断の内容は貨物軽自動車運転者等台帳に記録
- 保存方法は書面または電磁的手段
適性診断機関の選び方
この制度は、単なるチェックではなく、運転者の安全意識を高めるための実践的な教育です。
「診断機関の選び方」や「指導内容」なども重要です。
適性診断機関の選び方は、単に「近い場所」や「安い料金」で決めるのではなく、診断の質・信頼性・運用のしやすさを総合的に見て選ぶのがポイントです。
以下に、選定時のチェック項目を整理しました。
適性診断受診機関を選ぶ際のポイント
| チェック項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 診断の種類 | 初任・適齢・特定Ⅰ・特定Ⅱなど、必要な診断に対応しているか | 特定診断Ⅱは対応機関が限られる |
| 診断の信頼性 | 国交省指定機関か、NASVA(自動車事故対策機構)などの公的機関か | 民間機関でも国交省認定ならOK |
| 診断方法 | 対面・eラーニング・オンライン診断など、運用しやすい形式か | 地方事業者はオンライン対応が便利 |
| 診断内容の充実度 | 単なるテストだけでなく、助言・フィードバックがあるか | 事故惹起者には心理的要因への助言が重要 |
| 料金体系 | 診断料が明確かつ妥当か(相場:3,000〜6,000円) | 特定診断Ⅱは5,000円以上が一般的 |
| 予約のしやすさ | Web予約・電話予約・キャンセル対応などがスムーズか | 繁忙期は予約が取りづらいことも |
| 診断後の書類発行 | 診断結果の報告書がすぐに発行されるか | 運転者台帳への記録に必要 |
適性診断を実施している機関
適性診断を受診できるのは、国土交通省の認定を受けた機関です。
NASVA(自動車事故対策機構)や自動車学校などが、適性診断を実施しています。対応している診断は、診断実施機関によります。
診断実施機関の一覧は、国土交通省のホームページで確認できます。
> 国土交通省『適性診断認定機関一覧』
適性診断機関の選び方のコツ
- 複数の診断をまとめて受けたい場合は、NASVAなどの総合対応機関がおすすめ
- 事故惹起者の再教育を重視する場合は、心理的助言が充実した機関を選ぶと効果的
- 高齢者診断の場合は、加齢特性に配慮した診断項目があるかを確認