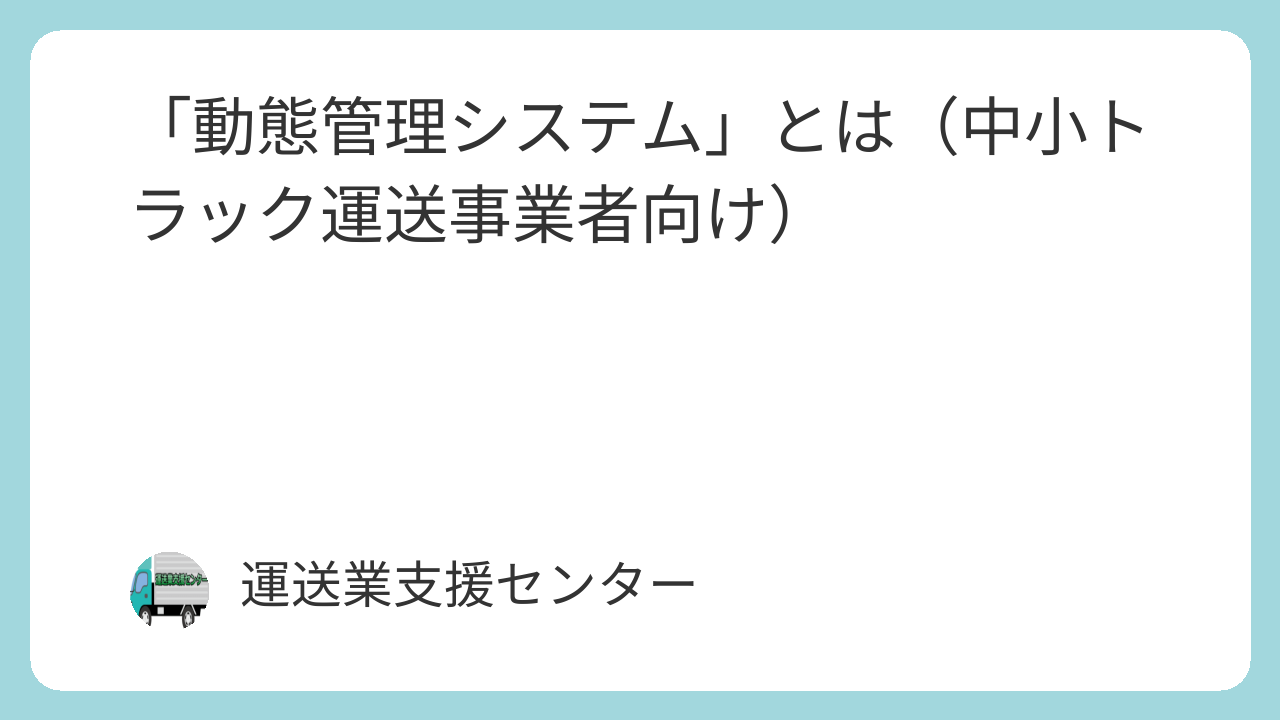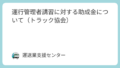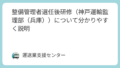中小トラック運送事業者が、動態管理システムを導入するためのガイドをわかりやすくまとめました。
(参考資料:全日本トラック協会『中小トラック運送事業者のためのIT機器・システム導入ガイド「動態管理システム」』)
動態管理システムって何?
- トラックの位置や運行状況を、営業所のパソコンやスマホでリアルタイムに確認できる仕組み。
- GPSで車の場所を把握し、インターネットを通じて情報を送受信。
- 荷物の温度やドライブレコーダーの映像も確認できるタイプもある。
動態管理システムとは、トラックの位置や運行状況をリアルタイムで把握できる仕組みです。車両に搭載したGPS機能付き端末から、インターネットを通じて営業所のパソコンやスマートフォンに情報が送られます。これにより、車両が今どこにいるのか、どんな状態で運行しているのかをすぐに確認できるようになります。
どんなメリットがある?
- 車が今どこにいるか、何をしているかがすぐにわかる。
- 荷主からの問い合わせにもすぐ対応できる。
- 地図で車の位置が見えるので、的確な指示が出せる。
- 安全運転や効率的な配車にも役立つ。
このシステムの最大のメリットは「輸送サービスの見える化」です。運行中の車両の位置や荷物の状態(温度・湿度など)をリアルタイムで把握できるため、荷主からの問い合わせにも即座に対応できます。また、地図上で車両の動きが見えることで、営業所からの指示も的確に行えるようになります。安全運行の推進や配車の効率化にもつながり、サービス品質の向上が期待できます。
導入方法は3パターン
| 導入方法 | 特徴 |
|---|---|
| 専用機器を使う | 車に専用端末を取り付けて使う。高機能で安定。 |
| デジタコ・ドラレコの追加機能として使う | 既存の機器に機能を追加して使う。コストを抑えられる。 |
| スマホ・タブレットを使う | 専用機器なしで、アプリとクラウドサービスで運用。導入が簡単。 |
導入方法は大きく分けて3つあります。
- 専用の車載端末とソフトウェアを使う方法。
これは高機能で安定した運用が可能ですが、初期費用がやや高めです。 - すでに導入しているデジタルタコグラフやドライブレコーダーに動態管理機能を追加する方法。
既存設備を活用できるため、コストを抑えられるのが特徴です。 - スマートフォンやタブレットを使う方法。
専用機器が不要で、アプリとクラウドサービスを利用することで、導入が比較的簡単です。
導入までの流れ
-
目的を決める
例:安全運転の強化、配車の効率化、荷主対応の改善など -
機器やサービスを選ぶ
国交省の認定機器一覧や補助金情報もチェック -
発注・設置・社内説明
関係者に目的を共有し、協力体制をつくる -
テスト運用 → 本格導入
運転手への操作説明、運行管理者の業務への組み込み
導入の流れは、まず目的を明確にすることから始まります。安全運行の強化、柔軟な配車、荷主対応の改善など、目的によって最適な導入形態が異なります。
次に、機器やサービスの選定を行います。国土交通省の認定機器一覧を参考にしたり、補助金の対象になるかどうかも確認しましょう。スマホやタブレットを使う場合は、必要なアプリやソフトウェアの開発も検討します。
その後、機器やサービスの発注・設置を行い、社内関係者に導入目的や活用方法を説明して協力体制を整えます。
最後に、運転者への操作トレーニングを実施し、テスト運用を経て本格的な稼働に移ります。運行管理者は、システムで得られた情報をもとに、どのような指導や対応を行うかを業務に組み込むことが重要です。
費用の目安(ざっくり)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 専用機器 | 車載器+取付費+通信料(月額) |
| スマホ・タブレット | 端末購入費+サービス利用料(月額) |
| オプション機能 | ETC、ドアセンサー、温度センサーなど |
費用面では、専用機器を使う場合は車載器の取付費用や通信料がかかります。スマートフォンやタブレットを使う場合は、端末購入費とサービス利用料が必要です。オプションとして、ETC車載器やドアセンサー、温度センサーなども追加できます。
このように、動態管理システムは中小運送事業者にとって、サービスの質を高め、安全性を向上させる強力なツールです。
導入の目的を明確にし、自社に合った方法を選ぶことで、現場の業務改善につながります。
動態管理システム導入チェックリスト
① 導入準備
- 導入目的を明確にした(例:安全運行、配車効率化、荷主対応強化)
- 単独導入か、既存機器(デジタコ・ドラレコ)との併用かを決定
- 自社のニーズに合った製品を選定するため、メーカーに相談
② 機器・サービスの検討
- 国交省認定機器一覧を確認
- 補助金対象かどうかを調査
- スマホ・タブレット利用の場合、必要なアプリやソフトを検討
- 導入費用(機器・通信料・工事費など)を見積もり、予算化
③ 発注・導入
- 性能・費用・導入時期を比較してメーカーを決定
- 必要なオプション(ETC、温度センサーなど)を選定
- 社内関係者に導入目的と活用方法を説明
- 意見交換を行い、協力体制を構築
④ テスト運用・本稼働
- 運転者に操作トレーニングを実施
- 運行管理者の業務にシステムを組み込む
- テスト運用期間を設定し、効果を確認
- 本稼働を開始